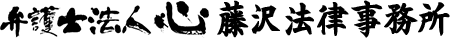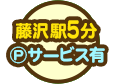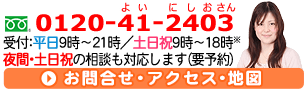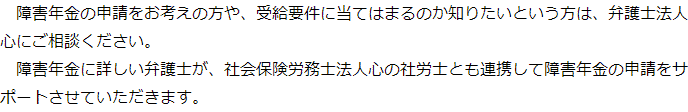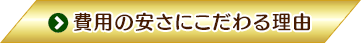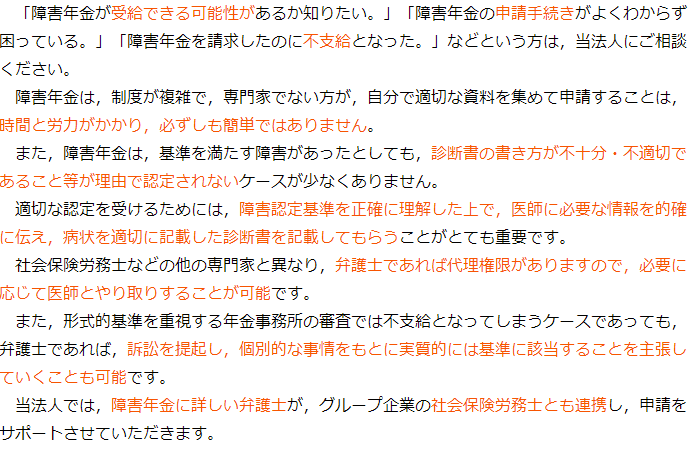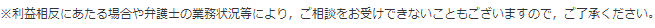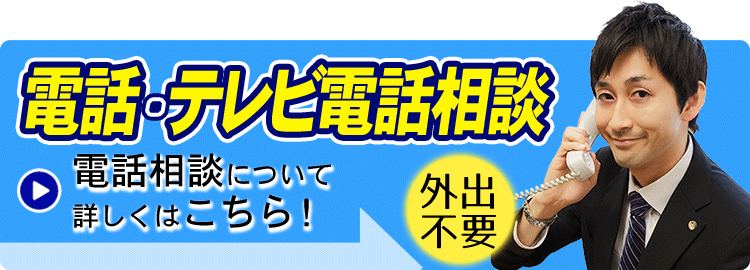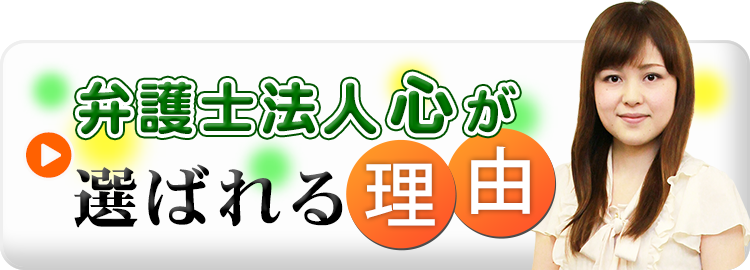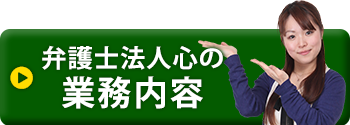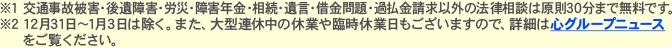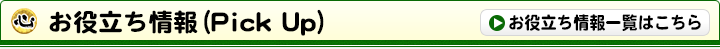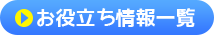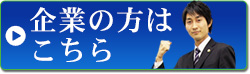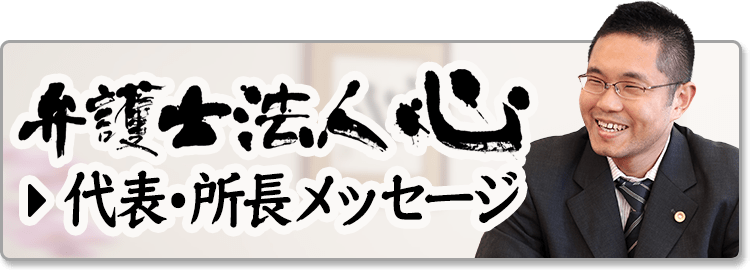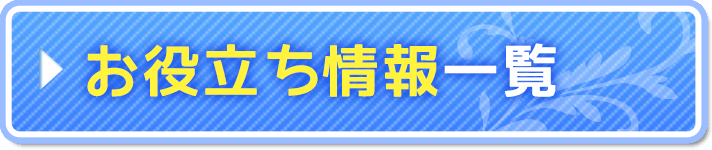障害年金
障害年金の所得制限
1 原則として所得制限はない

障害年金は国民年金や厚生年金等の保険料を納めていることを前提とした制度のため、原則として、所得制限はありません。
ご家族に収入があったとしても、関係ありません。
ただし、例外的に、所得制限がされる場合があります。
2 20歳前に初診日がある場合
20歳になる前に、障害の原因となる病気や怪我で初めて病院に行き、その初診日に厚生年金に加入していない場合には、例外的に、所得制限があります。
この場合には、国民年金の保険料をおさめていなくても、障害年金を受給することができるため、公平性を保つため、一定以上の所得がある場合には、障害年金の一部または全部が支給停止されることとなっています。
3 所得制限の内容
前年の所得額が472万1000円を超える場合には全額が支給停止となり、370万4000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。
扶養親族がいる場合には、扶養親族一人につき38万円が加算され、対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、一人につき48万円が加算され、特定扶養親族または19歳未満の控除対象扶養親族である場合には一人につき63万円が加算されます。
前年の所得額が制限額を超えると、10月分から翌年9月分までの1年間が支給停止となります。
その後、制限額未満に下がった場合は、翌年から支給が再開されます。
制限額を超えるかどうかは、毎年、日本年金機構が市区町村から所得情報を得て確認します。
支給停止も支給再開も日本年金機構で手続きをするため、原則、ご自身での手続きは不要です。
4 藤沢でお悩みなら当法人にご相談ください
障害年金を申請する上では、所得制限以外にも、注意しなければならない点がいくつもあります。
障害年金が支給されるかどうかは、書面により審査されるため、書面に不備があると、適切な等級が認定されないことになります。
障害年金の申請にご不安な点がある方は、一度、当法人までお問い合わせください。
障害年金を専門家に依頼するメリット
1 障害年金の申請を専門家に依頼することによるメリット

障害年金の申請は、申請する本人やそのご家族等で行うことも可能です。
専門家に依頼するとなれば、当然報酬等の費用もかかります。
それでも、専門家に依頼するのは、そこに依頼によるメリットがあるからです。
2 適切な方針で申請手続きを進めることができるようになる
例えば、障害年金申請の前提として、初診日の特定と保険料の納付という要件を満たしている必要がありますが、初診の病院が閉院していたり医療記録が残っていなかったりすると、初診日の証明が困難な場合があります。
対応は色々考えられますが、申請手続きについてよくわかっていないと、「初診日が特定できないから障害年金がもらえない」と考え、そこで終わってしまうこともあるでしょう。
どういう状況で、どのように対応すれば受給の可能性が出てくるのかは状況によって千差万別です。
個々の状況に応じた適切な方針選択ができるのは、専門家に依頼する場合のメリットといえます。
3 手続きの負担軽減
障害年金の申請にあたっては、必要書類の準備、書類の作成等が求められます。
書類の収集や作成の負担をどのように感じるかは人それぞれになると思います。
特に負担が大きいといえるのは、「病歴・就労状況等申立書」の作成になろうかと思います。
診断書等は医師に作成を依頼するものですし、各種公的書類等も集めれば済むものですが、病歴。・就労状況等申立書については、初診日前から(傷病によっては出生時から)現在までの症状の推移や通院、治療の経過、その間の就労状況等についてまとめる必要があります。
伝えたい内容をうまく文章にできない方や、逆にあれこれ書きすぎてしまい何を伝えたいのか分からなくなってしまう方等の場合には、専門家に端的にわかってもらいたい傷病の状況や経過などについてまとめてもらえるメリットは大きいといえます。
そのほか、収集可能な資料については専門家の方で集めてもらえるといった点も負担軽減につながるでしょう。
4 受給結果に影響を与える場合もある
障害年金の審査は日本年金機構で行われるため、受給の可否は最終的には審査結果に委ねられることにはなります。
しかし、例えば適切に事実関係を申告することで「社会的治癒」の主張が認められ、受給できないと思われた申請で受給が認められたり、障害の状態を適切に見てもらうことで、適切な等級での障害年金の受給が認められたりと、専門家に依頼することで結果に大きく影響を与える場合もないわけではありません。
審査は年金機構で行われる以上、結果次第ということにはなってしまいますが、結果に影響を与える可能性があることは、専門家に依頼するメリットといえます。
特に障害年金を急いだ方がよいケース
1 障害認定日から5年経過している場合

初診日から原則として1年6か月経過した日を、障害認定日といいます。
そして、障害認定日以後3か月以内の症状について記載された診断書を提出し、障害等級にあたるか審査してもらう請求手続を「認定日請求」といいます。
認定日請求により障害等級の認定がなされると、認定日が属する月の翌月分から障害年金をもらうことができます。
ただし、必ず認定日の翌月分からもらえるとは限りません。
障害年金を遡ってもらうことができるのは過去5年分に限られ、それ以前の分については消滅時効によりもらえなくなるからです。
障害認定日が到来しても、障害年金の請求できることを知らずに請求されない方も少なくありません。
仮に、5年以上経過している場合には、本来、もらうことができた障害年金がどんどん時効により消滅してしまっているので、障害年金の請求を早急に進める必要があります。
2 事後重症請求の場合
障害認定日時の症状は障害等級に該当しないものの、その後症状が悪化して障害等級の該当する程度の状態になったときは、そのときに障害年金の請求をすることができます。
これを「事後重症請求」といい、請求日前3か月以内の症状を記載した診断書を提出し、審査してもらいます。
事後重症請求により障害等級の認定がなされると、請求した月の翌月分から障害年金をもらうことができます。
請求が遅くなればなるほど障害年金をもらうことができる期間が短くなってしまいますので、事後重症請求の場合にも手続きを急いで進めなければなりません。
3 障害認定日から1年経過しそうな場合
障害認定日から1年以上経過して認定日請求をする場合、診断書が2通必要です。
障害認定日後3か月以内の診断書に加えて、請求前3か月以内の診断書も提出しなければなりません。
これに対し、障害認定日から1年以内に認定日請求をする場合には、障害認定日後3か月以内の診断書のみで足ります。
診断書をとりつける手前と費用の点から、障害認定日から1年経過しそうな場合には早急に請求した方がよいといえます。
4 弁護士・社労士にご相談ください
障害年金の請求手続きが遅くなると、先ほど述べたような不利益を被ることがあります。
障害年金の申請をお考えの場合には、お早めに弁護士や社労士にご相談されることをおすすめします。